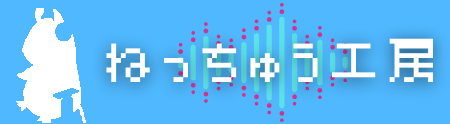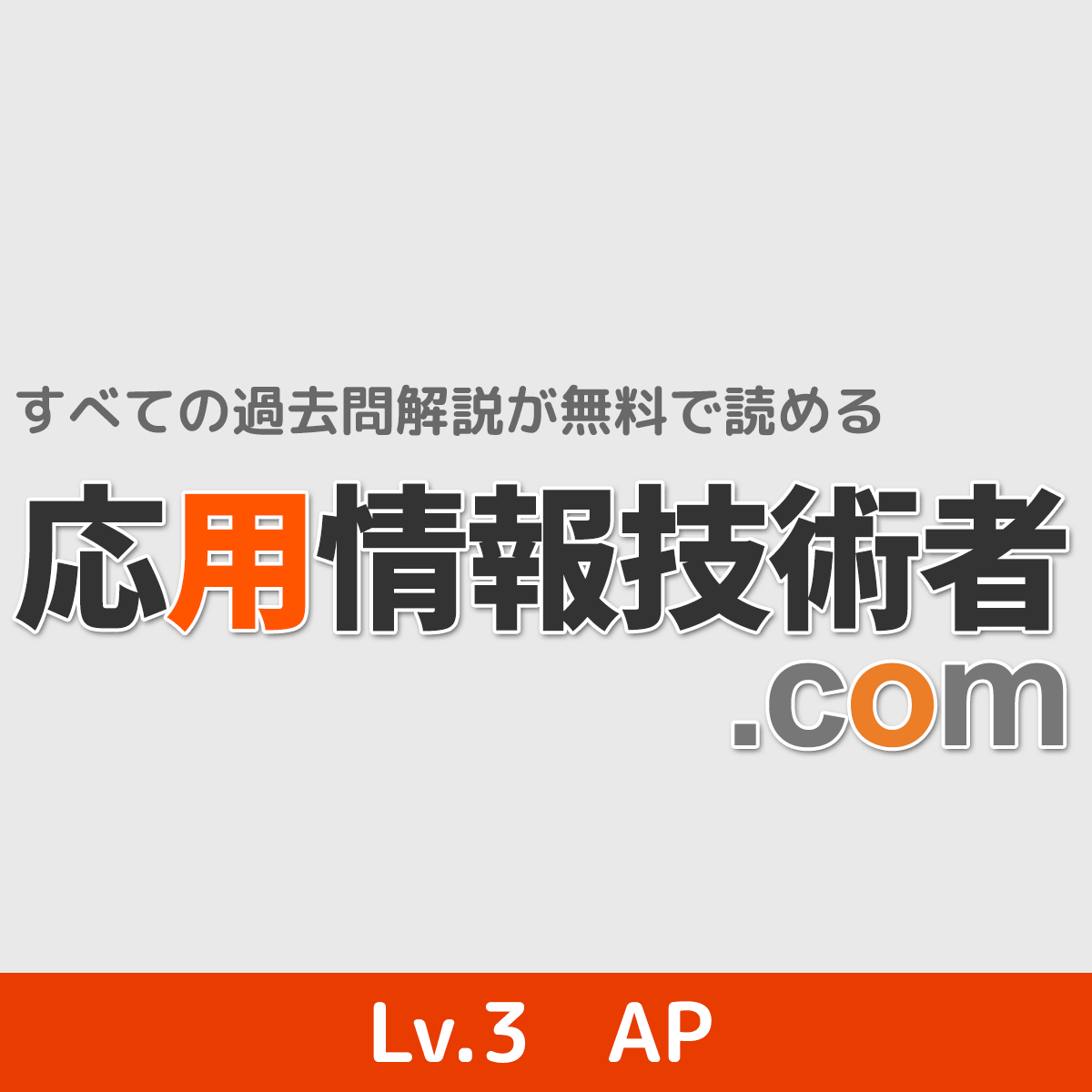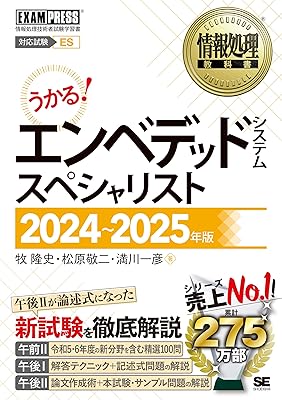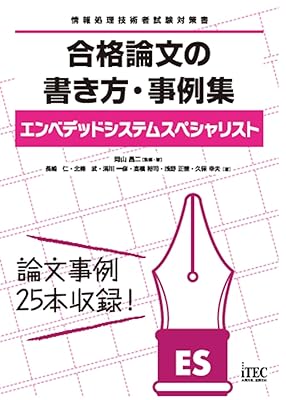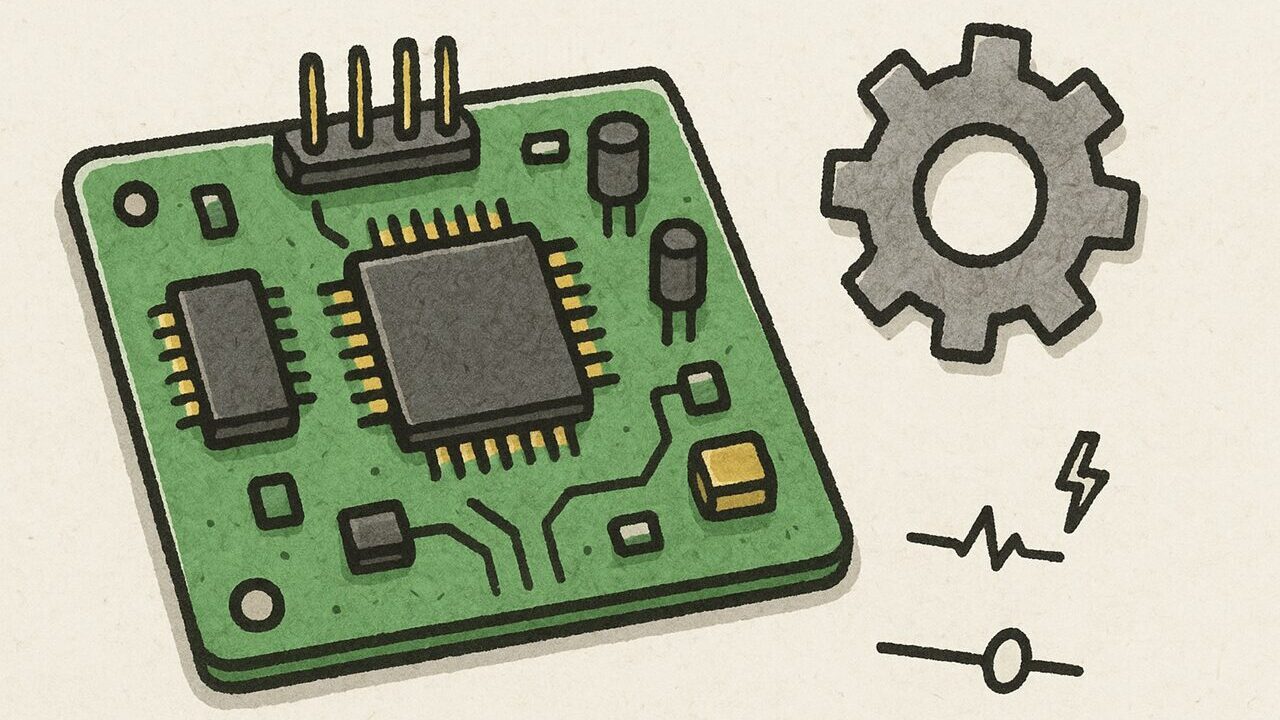
昨日(2025/10/12)、エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES試験)を受けてきました。正直言って、午前Ⅰと午後Ⅱがオワッテ、100% 受かっていないと思いますが、2025年度のES試験がどうだったか書き残そうと思います。
申し込み
2025年度のES試験については 7/11~7/30 が受験の申し込み期間でした。以下のリンクから申し込みました。
試験は年に1回しか実施されないため、基本情報のように気軽に再試験はできないです。
応用情報を合格済みの方は午前Ⅰの試験を免除できるようですが、筆者は学びなおしができると思い、午前Ⅰの試験を免除しませんでした。ただ、ES試験後は午前Ⅰを免除しておけばよかったと後悔しています。
出題される問題
ES試験では、午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰで合格基準点(60点/100点)を超え、午後Ⅱ という論述試験でAランクを取ることで合格となります。
● 午前Ⅰ
- 問題形式:4択問題
- 試験時間:50分
- 問題数:30問
午前Ⅰでは応用情報の午前試験とほとんど同じ問題が出ます。応用情報を合格した人は問題ないかと思いますが、甘くみていると筆者みたいに落とす可能性があります。
● 午前Ⅱ
- 問題形式:4択問題
- 試験時間:40分
- 問題数:25問
午前Ⅱでは応用情報の午前試験の組み込み関連の問題を集めたような試験となっています。過去問の中から4割ほど出てくるため、午前Ⅰよりも簡単なのではないかと個人的に思います。
● 午後Ⅰ
- 問題形式:記述式問題
- 試験時間:90分
- 問題数:1問(2問から1問選択)
午後Ⅰでは記述式の問題となります。とある開発製品の概要、機能の説明、システムの構成要素などを読んで記述式の問題を解くという形式になります。
8問くらいの記述式の問題が出され、3問くらいの計算問題が出る感じです。
● 午後Ⅱ
- 問題形式:論述式問題
- 試験時間:120分
- 問題数:1問(3問から1問選択)
午後Ⅱでは論述式の問題となります。組み込みシステム製品のあるテーマについて自分の経験を踏まえて論述する問題となります。
1問目で携わった開発製品の概要などを400字以上で説明、2問目であるテーマに関する開発時の工夫を800字以上で説明、3問目で開発の工夫についての評価を600字以上で説明するのを120分以内に行うという感じです。
勉強方法
各試験で使用した教材は以下のようになります。
● 午前Ⅰ
午前Ⅰについては応用情報の過去問演習で勉強しました。100問くらい解いて、7割弱くらいはいけるので、ギリ大丈夫だと思っていました。
● 午前Ⅱ
午前Ⅱについても過去問演習で主に勉強しました。8年分くらい解いて、8割くらいはいけるようになったので、午前Ⅱについては自信がありました。
● 午後Ⅰ
午後Ⅰについては、解き方がわからなかったので参考書を買いました。2年分解いて、6割ギリいけるというレベルです。
● 午後2
午後Ⅱについては、論述の方法がわからなかったので上記の参考書を買いました。ただ、論述に対して重い腰が上がらなかったので、ちゃんと読んだのは試験前日でした。前日に1問を6時間くらいかけて解きました。
試験当日
試験は9時半からでしたので、10分前に試験会場に到着していました。
● 午前Ⅰ
午前Ⅰを受けている最中はかなり絶望していました。自信もって解答できる問題がほとんどない...。得意なテクノロジー系の問題も勉強してきたところから外れた問題が出てくるし、マネジメント系やストラテジ系の問題は忘れているで散々でした。
問題としては以下のような問題でした。
- リバースプロキシの説明として,適切なものはどれか。
- サイバー攻撃の攻撃段階をモデル化したサイバーキルチェーンにおいて、”エクスプロイト”に該当する行為はどれか。
- NoSQLデータベースシステムに関する問題
- プロジェクトの人件費の増加量を求める問題
あらためて見返すとそこまで難しい問題ではなかったですが、知識があいまいであったため、解けなかったのかなと思います。
ストラテジ系やマネジメント系の勉強意欲は今後も出てこないと思いますので、来年は午前Ⅰは免除しようと思います。
● 午前Ⅱ
午前Ⅰに比べて相当簡単でした。過去問から5割くらい出てきたのに加え、問題の内容も簡単だったので、合格基準点はさすがに超えていると思います。
解けなかったのは以下のような問題です。
- DNSSECを導入したサーバーの動作に関する問題
- ソフトウェアプロダクトライン開発の説明を選択する問題
- 現実世界の物や状況を、現実世界から集めたデータをもとにサイバー空間上に再現する技術の名称を選択する問題(デジタルツイン)
● 午後Ⅰ
選択問題は以下のような2つの問題でした。
- 次世代一人乗り電動車椅子に関する問題
- 超小型人工衛星を用いた建設進捗状況を監視するシステムに関する問題
超小型人工衛星はとっつきにくいと思ったので、電動車椅子の問題を選択しました。過去問に比べて難しくはなく、時間内に全問の解答を書くことはできました。そのため、午後Ⅰも合格基準点は超えているかなと思います。
● 午後Ⅱ
選択問題は以下の3つでした。
- 問1. 新市場に対する製品企画におけるマーケティング戦略について
- 問2. 組込みシステム製品の流用設計について
- 問3. 組込みシステム製品における入出力インタフェースの開発について
筆者は音響機器の開発経験があったので、オーディオの入出力インタフェースの開発については書けると思い、問3を選択しました。
前日に論述を書いたのもあって、自分なりにスラスラと書いていたつもりでしたが、2時間は短すぎました。4割くらいしか書いていないのに時間が30分ほどになり、残りの30分で書いた論述は支離滅裂だったと思います。
やはり、2時間以内に論述を一度完成させ、だれかに添削してもらったほうが良かったなと思います。あとは2025年度からCBT方式になると勘違いしていて、筆記で練習しなかったのも反省点です。CBT形式は2026年度からなんですね。
試験結果
試験結果については 2025/12/25 に発表となりますので、そのときに追記いたします。
おわりに
本記事では ES 試験の振り返りを行いました。振り返るとES試験をなめてる勉強量でしたので、来年はきちんと勉強しようと思いました。特に論述はしっかりやろうと思います。
来年度から ES 試験はCBT形式になるので、論述がやりやすくなるのではないかと思っています。論述の試験中、今の時代に紙で論述する人はいるのか?という気持ちで受けていたので、そのストレスがなくなるのが嬉しいです。
来年、頑張ります!!